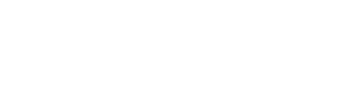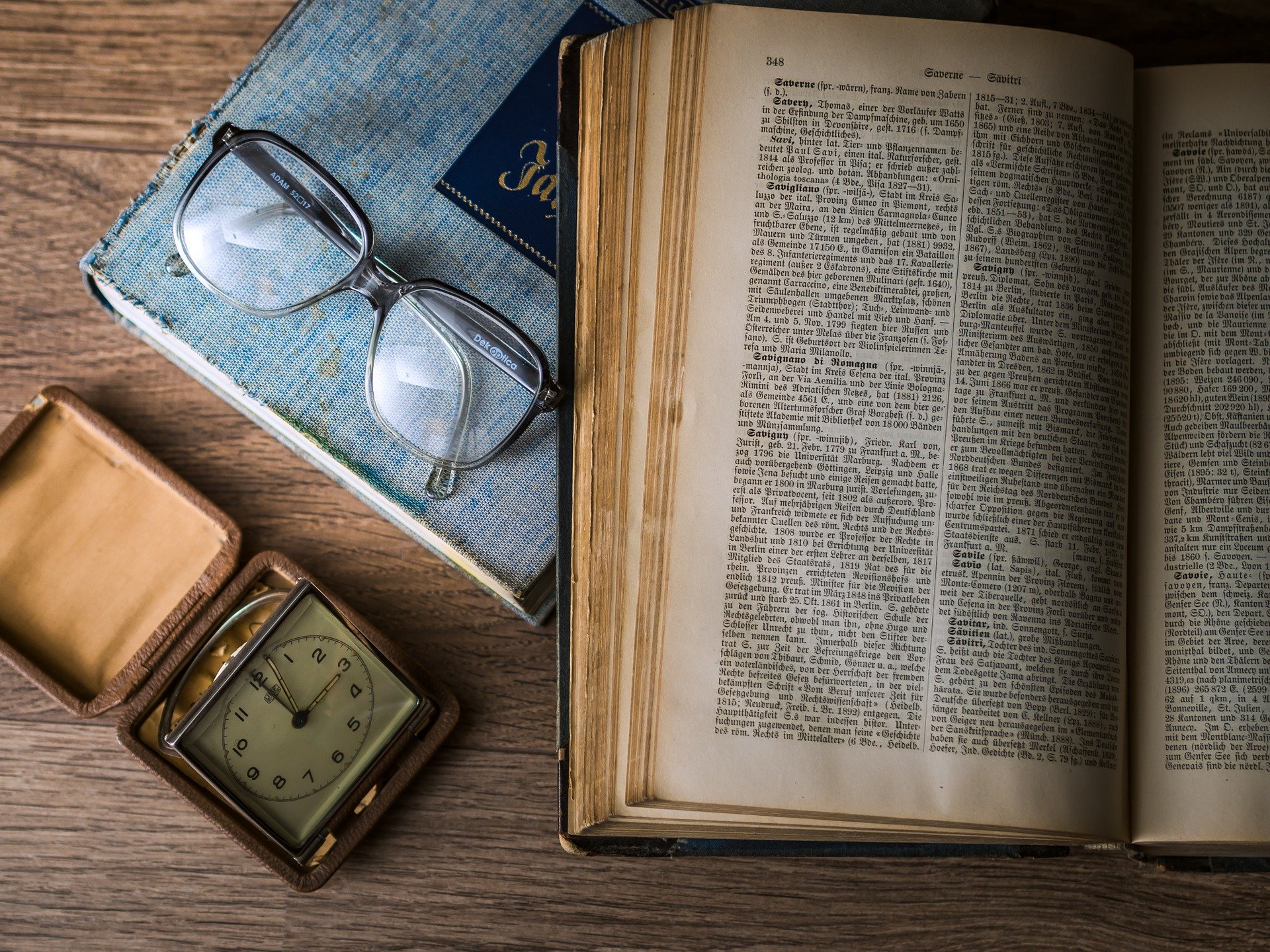僕はーーなんの力もない。人が死んでいくのをただ見てるだけだ。昔も今も何も変わっちゃいない。相変わらず僕は無力で、何もできない
こんにちわ、STAFF-Bです。
今回から、本の紹介をしていきたいと思います。
第2回目は、「首都感染」高橋哲夫 著 です。
作中で水際防御が破られたため、首都を封鎖することで議論するシーンがありましたが、
東京の封鎖は難しいという表現がありましたが、悲しいかな2020年、実現してしまいました(要請だったけど…)。
対処方法、薬の確保、感染者/死者数の数字の取り扱いについての公表について…
さまざまな議論のシーンがあり、今年、然るべきところではこうした物語が生まれたのだろうかとついつい想像してしまいます。
「首都感染」の見所
読書後に、どうしてノンフィクションの作品がどこんなにも現実になってしまいやすいのか考えてみました。
この著者はもしかしたら、歴史を振り返る中で人間の本質を描写することで未来の歴史をうまく作品にされているのかもしれませんね。
コロナ渦のまえに読みましたが、こうも似てくる世界線というのがあるものだな、と考えされられました。
「首都感染」の評価
あくまでも作品はフィクションのため、物語として終わりますが、現実世界はまだつづていきますので、これを読みながら今一度、対策や日々の取り組みについて気を引き締めたいと考え直すのに十分な作品でした。
また、危機管理のあり方についていうと、様々なケースを想定しておかなければならないため、フィクションではありますがそうした一つのケースとして読んでみてはいかがでしょうか。
(いまの時代だと半分フィクションっていうのが正しいのかもしれませんが)
—
2020年11月22日 更新
思ったよりも手強いコロナの影響で、ノンフィクションだった作品がフィクションになろうとしているかのようです(致死率が異なるので、緊張度が異なりますが・・・)。
経済への影響も長引いてきていますが、この本のように素早く解決には至りません。
いま一度、危機管理のあり方も見直したいところですが、やはり今年のゴールデンウィークの頃の、緊張感をもう一度持つべきなのでしょうか。
半年も経つと、ゴールデンウィークの頃の緊張感や空気感というものを思い出し辛くなってきています。
人の記憶というのは曖昧なものなので、読書をしながら緊張感を少しでも取り戻して、今一度、見えない脅威への対策を考え直すきっかけにしたいですよね。

IT-POP スタッフBです。
読書の話題を中心に記事を投稿しています。